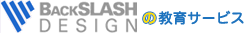セミナー一覧
| セミナー名 | 概要 |
|---|---|
| AtScope体験会
資産価値向上 |
AtScopeを使って既存コードのアーキテクチャ再構築を体験します。 |
| 設計図フォーラム [第11回]
設計力向上資産価値向上 |
設計図を活用することで商品開発の成功と人材育成を両立するための情報交換の場です。 |
| Cプログラミング(新人研修)
設計力向上 |
前半3日間で構造化プログラミング、後半2日間でモジュール化を習得します。 |
| 設計技法基礎(新人研修、2年目研修)
設計力向上 |
設計図を作成し、プログラミングすることで、設計と実装を同時に習得します。 |
| 設計実装PBL(新人研修、リスキリング研修)
設計力向上 |
プロジェクト推進での分析設計実装テストと報告を実践します。 |
| 分析設計テスト実習(2年目~5年目研修)
設計力向上 |
5日間で分析、設計、実践、テストの必要性と手順を理解します。 |
| モデリング概論
設計力向上 |
本講座では、構造化モデリング/オブジェクト指向モデリング/システムズモデリングについて、開発工程ごとのモデルとその表記法を習得します。 |
| 設計図活用
設計力向上 |
ハードウェアを制御するC言語のソースコードを図面化します。既存ソースコードの問題点を見つけ設計構造を改善します。 |
| 使える!リアルタイムOS
設計力向上 |
組込みシステムの時間制約や並行処理を実現する手段のひとつとしてリアルタイムOS (RTOS) の概要を学びます |
| 構造化モデリング[静的]
設計力向上 |
要求、分析、設計の各工程ごとに、モデル化の視点を明確にして、図面作成を行います。上流工程での分析・設計の勘所を習得します。 |
| 設計図を活用した派生開発
資産価値向上 |
設計図を活用した派生開発を学ぶ講座です。 |
| 構造化モデリング[動的]基礎
設計力向上 |
時間軸を考慮した設計の基本習得します。 |
| 構造化モデリング[動的]実践
設計力向上 |
ループを回すサイクリック実行型とタスクで動くイベント駆動型の特徴を理解します。実行単位の設計、状態遷移の設計を演習します。 |
| オブジェクト指向モデリング
設計力向上 |
オブジェクト指向の設計要素であるクラスを理解します。C言語でのクラス設計を演習し、オブジェクト指向の開発をひと巡りします。 |
| アーキテクチャ設計基礎
設計力向上 |
アーキテクチャ設計で使う図面(静的/動的/状態)を読み書きします。 |
| アーキテクチャ設計実践
設計力向上 |
システム全体構造の設計方法、及び設計内容を伝達するための設計図法を習得します。アーキテクチャ設計として、複数ビューで図面化します。 |
| アーキテクチャ設計実践:異常系編
資産価値向上 |
異常系のアーキテクチャ設計講座です。 異常系の要求を定義して、異常発生の検出と、異常除去後の復帰/異常終了の設計図を作ります。 |
| アーキテクト活動クイックスタート
設計力向上資産価値向上スキル強化 |
既存コードを基点にアーキテクト活動を開始することができます。 |
| アーキテクト育成
設計力向上 |
製品のコンセプトを明確にし、設計の方針を立て、その設計図面を作る、という一連の流れを演習を通じて学習します。経営と技術をつなぎます。 |
| 凝集度と結合度
資産価値向上 |
「凝集度」と「結合度」と呼ばれる品質尺度を、演習を通じて実践・体得することができます。ピアレビューでの視点として役立ちます。 |
| リバースモデリング
資産価値向上 |
ソースコードを保守性の高いソフトウェア資産にするためのソースコード改善のテクニックを習得します。リファクタリングとリバース設計。 |
| リファクタリング基礎
資産価値向上 |
C言語のソースコードの資産価値を高めるリファクタリングを学びます。 |
| リバース設計
資産価値向上 |
C言語のソースコードの資産価値を高めるリバースモデリングを学びます。これによりソフトウェアの資産化ができ、生産性と品質を格段に上げることができます。 |
| リファクタリング実践(部品化リファクタリング)
資産価値向上 |
関数/ファイル/フォルダという3つの粒度でリファクタリングして、構造化された設計図を作ります。PCを使った演習で実践します。 |
| アーキテクチャ改善(リ・アーキテクティング)
資産価値向上 |
構造のリファクタリングでアーキテクチャ構造を見える化し改善します。 |
| ソフトウェア資産化
資産価値向上 |
共通部を定義しインタフェースを決める「プラットフォーム化」と変動部を定義し置換方法を決める「プロダクトライン化」を習得します。 |
| 要求モデリング実践
資産価値向上 |
図表ファーストでの要求定義方法を習得します。 |
| C言語セキュアコーディング
ドメイン特化 |
セキュリティ視点でのプログラム上の弱点(脆弱性)について理解し、脆弱性を排除するセキュアなプログラムの書き方について学習します。 |
| 脅威分析とセキュア開発
ドメイン特化 |
守るべき資産と脅威を関連付けし、リスク値に応じた対策例を演習します。 |
| 単体テスト技法
設計力向上 |
C言語の関数単位での単体テストケース設計を習得します。 |
| レビュー技法
スキル強化 |
上流工程でのレビューについて、演習を通して理解・習得します。 ピアレビューの基本を理解した上で、PBR査読法を習得します。 |
| 結合テスト技法
スキル強化 |
結合テストの基礎と結合テスト設計技法「RiTMUS法」を学習します。 |
| バージョン管理Git入門
トレーニング |
ソフトウェア開発におけるバージョン管理の必要性、バージョン管理システムの仕組みを理解する講座です。 |
| 良い設計良いコード トレーニング
設計力向上トレーニング |
「良い設計」と「良いコード」を見て学ぶ1日コースです。 |
| 抽象化トレーニング
トレーニング |
制御仕様をそのままプログラミングするのではなく、問題ドメインの本質を分析することで、構造的なソースコードになることを体験します。 |